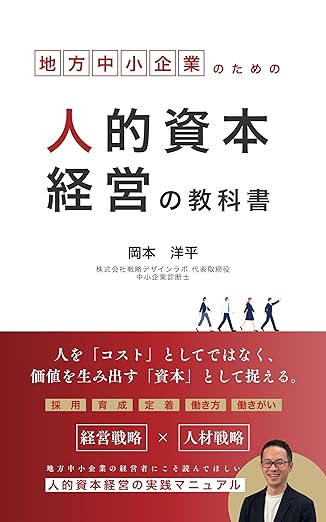「人的資本経営」という言葉、最近ニュースやビジネス誌で皆さまもよく見かけるのではないでしょうか。しかし、地域の中堅・中小企業の経営者様の多くは、少し複雑な思いでこの言葉を見ているのではと思われます。
「大企業の話だろう」 「うちは人事部すらないのに、そんな余裕はない」 「重要性はなんとなく分かるが、具体的に何から手を付ければいいのか分からない」
もしそのように感じられたとしても、それは無理もないことです。日々の業務に追われる中で、目に見えにくい「人」への投資を戦略的に行うことは、非常にハードルが高く感じられるからです。
しかし、その上で断言します。人的資本経営こそ、リソースの限られた中小企業が生き残るための「唯一の生存戦略」なのです。本コラムでは、株式会社戦略デザインラボの実践事例とノウハウに基づき、中小企業がどのように人的資本経営の一歩を踏み出せばよいのか、その具体的な道筋をお伝えします。
なぜ今、中小企業に「人的資本経営」が必要なのか
まず、現状の厳しさを直視する必要があります。多くの中小企業経営者様が肌で感じていらっしゃる通り、経営課題のトップは「人」にあります。
実際に企業の声を分析すると、経営課題の上位4つのうち、実に3つが人材に関する課題で占められているというデータがあります。具体的には「とにかく人手が足りない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「リーダーが育たず組織の生産性が上がらない」といった悲痛な叫びです。
さらに恐ろしいのは「黒字廃業」のリスクです。利益が出ているにもかかわらず、深刻な人手不足や後継者不在によって事業継続を断念せざるを得ないケースが急増しています。また、人材確保のために賃上げは不可欠ですが、それを上回る生産性の向上が伴わなければ、経営は圧迫される一方です。
かつてのように企業が労働力を「選ぶ」時代は終わりました。これからは、企業が働き手から「選ばれる」時代です 。人材をコスト(費用)ではなく、投資すべき「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出す経営への転換。それこそが、これらの危機を回避する唯一の道なのです。
立ちふさがる「3つの壁」と、その乗り越え方
では、なぜ多くの企業で取り組みが進まないのでしょうか。そこには3つの大きな壁が存在します。
一つ目は「知識のギャップ」です。部分的に研修などを実施していても、網羅的・体系的に取り組めていないケースです 。
二つ目は「認識のギャップ」です。重要性は頭で分かっていても、目先の売上などと比べて緊急性が低いと判断し、後回しにしてしまう心理的な壁です 。
そして三つ目が「リソースのギャップ」です。人、モノ、カネ、時間といった余裕がなく、継続的な取り組みが難しいという物理的な壁です 。
これらの壁を自社だけの努力で乗り越えるのは容易ではありません。しかし、正しい手順(ロードマップ)を知ることで、着実に前に進むことができます。
取り組みを進めるための「6つのステップ」
人的資本経営を体系的に進めるためには、拙著『地方中小企業のための人的資本経営の教科書』でも提唱している、以下のステップに沿って進めることが推奨されます。
ステップ0:経営戦略との紐付け
これが最も重要です。単に福利厚生を良くするということではありません。会社の「経営戦略」を実現するために、どのような人材に来てほしいか、育ってほしいか、定着してほしいかを定義することから始まります。
ステップ1:ゴールの設定(To-Be)
会社が目指す理想の姿を明確にします。例えば、「5年後に地域で知名度No.1になる」「10年後に地域課題を解決する複合体になる」といったビジョンです。そのビジョンに向け、どの役職・部門にどのような人材が必要になるのかを、見える化してみましょう。
ステップ2:現状の見える化(As-Is)
理想に対して、今の自社はどうなっているかを直視します。従業員の年齢構成、離職率、エンゲージメント(働きがい)の状態などを数値化して把握します。難しいようでしたら、採用・育成・定着のそれぞれにおける現状を箇条書きにしてみると良いでしょう。
ステップ3:ギャップ分析と課題特定
理想と現実の間にある「ギャップ」こそが、取り組むべき経営課題です。何が原因(今の状況を引き起こしている本質的な問題)で、何が課題(原因をもとに、これから何に取り組まなければいけないのか)を明らかにする必要があります。
ステップ4:人材戦略の策定
特定された課題を埋めるための戦略を立てます。採用を強化するのか、今いる社員の育成に力を入れるのか、あるいは定着率を高める施策を打つのかを決定します。
ステップ5:アクションプランの策定
戦略を具体的な行動計画に落とし込みます。アクションプランは「実行可能」な状態まで具体化することが大事です。いつ、どこで、誰が、誰と、何を、どのように、いつまでにが具体化できていると、実効性のあるアクションプランとなるでしょう。
ステップ6:PDCAおよび人的資本開示レポート作成
計画を実行した後に振り返りを行い、その結果を社内外に公表します。公表に際しては「人的資本開示レポート」が最も良い手段です。特に第三者の目を入れながら作成すると、客観性・信頼性のあるレポートとなります。
従業員10名の会社でもできる! 戦略デザインラボの実践事例
「手順は分かったが、やはり大企業向けの話ではないか?」 と思われるかもしれません。しかし、私ども株式会社戦略デザインラボでは、人的資本経営の取り組みを数多く実施しています。
当社は役員・スタッフ合わせても10名強という規模ですが、「経営のワンストップコンシェルジュ」を掲げ、自らも実験台となって様々な取り組みを行っています。
特に注目すべきは、トップダウンではなくスタッフの声から生まれた制度が多い点です。その代表例が「親子出社制度」です 。子育て中のスタッフが働きやすいよう、子供と一緒に職場に来て仕事ができる環境を整えました 。これは、従業員の多様なライフスタイルを尊重し、働きやすさを追求する「ダイバーシティ&インクルージョン」の具体的な実践と言えます。
また、人材育成においては「週1回の社内勉強会」や「年2回の全体研修」を継続的に実施しており、学びと成長の機会を全員に提供しています。さらにユニークなのは、コンサルティング事業だけでなく、バルーンギフト事業も行っており、スタッフは自身の強みや生活に合わせて柔軟に活躍の場を選択できることです。
これらの取り組みの結果、同社の従業員アンケート(エンゲージメント調査)では、「働きやすい環境」で4.5点、「人事評価・キャリア形成」で4.45点(5点満点)という高いスコアを記録しています。これは、規模が小さくても、経営陣が本気で向き合えば、従業員の働きがいは確実に向上することを示しています。
「人的資本開示レポート」がもたらす4つのメリット
人的資本経営に取り組んだら、その内容を「人的資本開示レポート」として社外に発信することを強くお勧めします。これは上場企業だけの義務ではありません。中小企業が自発的に開示することで、以下の4つの大きなメリットが得られます。
一つ目は「自社のブランド力の向上」です。「人を大切にする会社」としての姿勢を明確に示すことで、顧客や取引先からの信頼感が高まります。
二つ目は「社内エンゲージメントの向上」です。 会社が従業員のために何に取り組んでいるかを可視化することで、社員の帰属意識やモチベーションが高まります。レポート作成プロセス自体が、経営陣と社員の対話のきっかけにもなります。
三つ目は「経営の改善ツールとしての活用」です。 レポートを作るためには、自社の現状を数値化(見える化)する必要があります。これにより、感覚的な経営から、データに基づいた客観的な経営へと脱皮することができます。
四つ目は「ステークホルダーからの信頼性の向上」です。 金融機関や地域社会に対し、透明性の高い経営を行っていることをアピールでき、融資や連携などの面で有利に働く可能性があります。また、採用活動においても、求職者に対して「安心して働ける会社」であることを強力にアピールする材料になります。
3年後ではなく、「未来への投資」を今すぐに
人的資本経営は、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、だからこそ「今」始める必要があります。「忙しい」を理由に先送りにすれば、3年後には手遅れになっているかもしれません。
まずは、自社の経営戦略と人材戦略が紐づいているか、経営者様ご自身が問い直すところから始めてみてはいかがでしょうか。そして、もし自分たちだけで進めるのが難しいと感じたら、専門家の伴走支援を活用するのも賢明な判断です。
株式会社戦略デザインラボでは、戦略策定から実行、そしてレポート作成までをワンストップで支援しています 。自社で実践し、成果が出ているノウハウに基づいた「血の通った支援」が可能です。
人材への取り組みは「コスト」ではなく、企業の未来を創るための「投資」です 。 「人が集まり、育ち、根付く会社」へ。 貴社の未来を変える一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう。
人的資本経営に関するご相談、人材課題(採用・育成・定着)に関するご相談、そして人的資本経営に取り組む前の経営改善に関するご相談まで、お気軽にお問い合わせください。初回訪問によるヒアリング・見える化は無料で実施させていただきます。
著者:株式会社戦略デザインラボ 代表取締役 中小企業診断士 岡本洋平